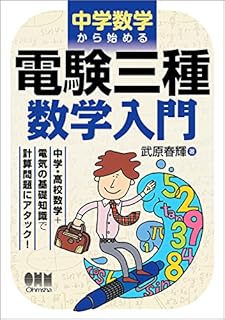エネルギー管理士になって5年以上経ちました。実際にエネルギー管理士になってみて、施設のエネルギー管理士に選任されてみてわかるようになったこと、見えてくるようになったことが多くなったので、ここらで書き記してみます。エネルギー管理士試験の説明や電気、熱課目の攻略方法なども書いていますので、ぜひご覧下さい。
エネルギー管理士とは
エネルギー管理士試験に合格またはエネルギー管理認定研修を修了して、エネルギー管理士免状の交付を受けている者です。建築物の省エネ診断及び省エネ提案、一定規模以上の建築物(エネルギー管理指定工場等一種又は二種)のエネルギー使用量の削減に取り組むことを主な業務としています。
エネルギー管理士の根拠法律
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下省エネ法)によりエネルギー管理士制度は定められています。 省エネ法では、一定量以上のエネルギー使用工場又は事業場は、エネルギー管理指定工場等(一種・二種)に指定され、そのうちの第一種エネルギー管理指定工場(事務所、オフィスビル等を除く製造業等の5業種)はエネルギーの使用量に応じて、エネルギー管理士免状の交付を受けている方のうちから、1人から最大4人のエネルギー管理者を選任しなければなりません。
エネルギー管理士が必要な施設
エネルギー管理士が必要な施設は、とエネルギー管理士の選任が必要なのは製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給量、熱供給業(以下製造業等5業種という)の施設で年間エネルギー消費量が原油換算で3,000kl以上の施設です。
| エネルギー使用量 | コークス製造業、電気供給量、 ガス供給業、熱供給業 | その他の製造業、 鉱業 | 左記の業種の事務所、 その他の業種 |
| 100,000kl以上 | エネルギー管理士(2人) | エネルギー管理士(4人) | エネルギー管理士又は員(1人) |
| 50,000kl以上 | エネルギー管理士(1人) | エネルギー管理士(3人) | |
| 20,000kl以上 | エネルギー管理士(2人) | ||
| 3,000kl以上 | エネルギー管理士(1人) | ||
| 1,500kl以上 | エネルギー管理士又は員(1人) | ||
| 1,500kl未満 | – | ||
詳しくはこちら エネルギー管理士(エネ管)が必要な施設をまとめてみました
参照サイト:省エネルギーセンター
エネルギー管理士の業務
①省エネ診断
エネルギー管理士のメイン業務と言えばこれです。建築物の中をくまなく現地調査し、エネルギーを使い過ぎているところが無いか、どれくらい使い過ぎていて、どうすれば省エネできるかを見定めます。 照明の点灯スケジュールを変更する、空調の運転スケジュールを変更するなどといった運用方法の変更で改善できるものについては速やかに実施し、ポンプのプロペラ(インペラ)をカットする、照明器具をLEDにする、二酸化炭素検知装置とファンを設置する等といった投資と工事が発生する改善策については、建築物の所有者に提案をして決裁を待って行います。
②エネルギー管理標準の作成
エネルギー管理標準とは
エネルギー管理標準とは、省エネ法によってエネルギー管理指定工場等で義務付けられている施設内のエネルギーの使用の合理化を図るための機器の点検、整備、管理の総合的な指針、ルール、マニュアルです。これがあることによって、施設内の多くの作業員が同一の水準でメンテナンスをすることができ、省エネに関連する設備が同一の周期で更新されることができます。
省エネルギー会議への参加及び意見陳述
エネルギー管理標準を作成するうえでは、月に1度以上の省エネルギー会議を行うことが推奨されており、実際に多くの現場のエネルギー管理標準の中には月に1度以上省エネルギー会議を開催する旨が記載されています。省エネルギー会議で司会を行い会議の進行をするとともに、先月とのエネルギー使用量の比較、前年同月とのエネルギー使用量の比較、最近行った省エネ施策の効果測定、最近の省エネの課題、今後行う省エネ施策等を話し合います。 会議の参加者は、選任されているエネルギー管理士、現場の設備員、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、その他施設関係者となる場合が一般的です。
エネルギー使用に関する定期報告書の作成・提出
エネルギー管理士は選任されているエネルギー管理指定工場等の年間のエネルギー使用量に関する報告書を作成し、経済産業省に提出しなければなりません。その報告書を作成するうえでのデータ収集、資料作成そして提出はエネルギー管理士の職務になります。
エネルギー管理士試験制度
| 試験実施団体 | 一般財団法人省エネルギーセンター |
| 民間資格or国家資格 | 国家資格 |
| 受験資格 | 無し |
| 受験料 | 17,000円(非課税,平成27年度実績) |
| 開催頻度 | 年1回 |
| 申込時期 | 5月上旬~6月上旬の間で申し込み |
| 試験時期 | 8月上旬 |
| 試験日程 | 1日(4コマ) 1限目9:00~10:20(80分) 2限目10:50~12:40(110分) 3限目14:00~15:50(110分) 4限目16:20~17:40(80分) |
| 試験形式 | 択一式(マークシート) |
| 合格基準 | いずれの課目も60% |
| 試験会場 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、富山市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市(平成27年度実績) |
課目(科目)合格制度
課目別の得点が合格基準(各課目60%)に達した課目は「課目合格」となり、4課目合格すればエネルギー管理士試験合格となる。課目合格は、その試験が行われた年の初めから3年以内に受験する場合、その課目の試験が免除になり、合格した年の初めから3年を過ぎるとその課目の合格は無効となる。
試験課目
必須基礎課目
I. エネルギー総合管理及び法規 (エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令、エネルギー総合管理)
選択専門課目
熱分野
II. 熱と流体の流れの基礎 (熱力学の基礎、流体工学の基礎、伝熱工学の基礎)
III. 燃料と燃焼 (燃料及び燃焼管理、燃焼計算)
IV. 熱利用設備及びその管理 (計測及び制御、熱利用設備)
電気分野
II. 電気の基礎 (電気及び電子理論、自動制御及び情報処理、電気計測)
III. 電気設備及び機器 (工場配電、電気機器)
IV. 電力応用 (電動力応用、電気加熱、電気化学、照明、空気調和)
合格率
| 年度 | 平成 | 電気分野合格率 | 熱分野合格率 |
| 1997 | 9年度(H9) | 23.2% | 41.2% |
| 1998 | 10年度(H10) | 25.8% | 33.8% |
| 1999 | 11年度(H11) | 18.8% | 33.6% |
| 2000 | 12年度(H12) | 24.8% | 31.5% |
| 2001 | 13年度(H13) | 23.8% | 29.0% |
| 2002 | 14年度(H14) | 24.7% | 37.2% |
| 2003 | 15年度(H15) | 24.7% | 40.4% |
| 2004 | 16年度(H16) | 32.1% | 36.5% |
| 2005 | 17年度(H17) | 23.1% | 28.2% |
| 2006 | 18年度(H18) | 21.1% | 26.7% |
| 2007 | 19年度(H19) | 22.5% | 27.6% |
| 2008 | 20年度(H20) | 15.0% | 25.6% |
| 2009 | 21年度(H21) | 29.7% | 29.4% |
| 2010 | 22年度(H22) | 25.4% | 43.1% |
| 2011 | 23年度(H23) | 21.8% | 18.2% |
| 2012 | 24年度(H24) | 16.7% | 28.0% |
2013年以降は電気分野、熱分野合算しての発表となっている。
| 年度 | 平成 | 合格率 |
| 2013 | 25年度(H25) | 27.9% |
| 2014 | 26年度(H26) | 21.5% |
| 2015 | 27年度(H27) | 23.3% |
| 2016 | 28年度(H28) | 20.1% |
エネルギー管理士の難易度
偏差値上での評価
設備・工業系資格を偏差値で表すと、電験三種:58、エネルギー管理士:59、電験二種:60で表されることがあるようです。そういうランキングを参考にして、エネルギー管理士の電気に関しては、電験2.5種と例えられることがあるようです。
電気分野の偏差値に関しては実際に電験三種とエネルギー管理士の電気を受験したことがある自分からは妥当な数値だと思います。
熱分野に関しては、2013年以降に電気分野と熱分野の合格率が統合して発表されるようになる以前は合格率が約25%となっており、電気分野の約15%と比較すると10%程度高くなっています。熱分野を実際に受検して合格した同僚2名の意見としては、「電気より熱の方が簡単だと思うけど、やっぱりエネルギー管理士試験だからそれなりに難しい。特に[II. 熱と流体の流れの基礎]についてはてこずった。」ということでした。
熱分野の偏差値的には1ポイント下がって電験三種と同程度の58ポイントか、もう少し下になるのかもしれません。
電気分野の内容の難しさ
私のエネルギー管理士受験は電気でしたが、確かに電験三種よりかは数式展開のレベルは高いと感じました。つまり数学力が必要とされます。高校数学が苦手だった人は、高校数学の参考書または電験三種の数学参考書を傍らに置いて勉強すると良いでしょう。
電験三種と比較すると過去問と同じパターンの問題が出題される傾向は強いです。過去問に素直な試験だと言えるでしょう。過去問10年分、できれば15年分の出題パターンをよく吟味して、過去問を出題パターン別に攻略していくと効率的でしょう。
熱分野の難しさ
熱分野の難しさは、やはり前述の[Ⅱ.熱と流体の流れの基礎]にあります。この課目の“熱力学の基礎”と“流体工学”に苦手意識を感じ、攻略の困難性を感じる人が多いようです。 勉強に行き詰まった場合は、わかりやすく書かれた良参考書が状況を打破してくれます。こちらの参考書が合格者の中で評価が高いようです。
勉強のコツ
電気分野、熱分野に共通して言えるのは、合格までに大量の数式を記憶して、試験期間中はずっと記憶を保持しなければならないことです。数式の暗記とその記憶の保持無くして、問題演習や過去問攻略に至ることはできません。
でも、大量の数式の記憶って工夫しないと結構大変です。私がおススメしたいのは中高生の時に英単語とその意味を単語カードの表と裏に書いて暗記していた人がいたように、数式の暗記もカード化してしまう方法です。
最初にカード化するときはちょっと手間ですが、そんな大した労力ではありませんし、一度作ってしまえば電車の中でも、バスの中でも、喫茶店でも、会社の始業時間前でも細切れ時間に記憶のメンテナンスをすることができるのでとにかくおすすめです。
勉強順序
勉強順序は結構大事です。課目同士で内容につながりがあり、ある課目の理解が他の課目の勉強を助けるということがありますし、難易度から考えたときも簡単でとっついやすい課目から攻略したほうが挫折しにくいでしょう。
電気
II. 電気の基礎 (電気及び電子理論、自動制御及び情報処理、電気計測)
III. 電気設備及び機器 (工場配電、電気機器)
IV. 電力応用 (電動力応用、電気加熱、電気化学、照明、空気調和)
電気は素直Ⅰ→II→III→IVの順番が良い様に思います。難易度が優しい課目から攻略する手法です。
熱
III. 燃料と燃焼 (燃料及び燃焼管理、燃焼計算)
IV. 熱利用設備及びその管理 (計測及び制御、熱利用設備)
II. 熱と流体の流れの基礎 (熱力学の基礎、流体工学の基礎、伝熱工学の基礎)
熱はⅠ→III→IV→IIの順番が良い様に思います。一番難しいとされる[II. 熱と流体の流れの基礎 (熱力学の基礎、流体工学の基礎、伝熱工学の基礎)]は最後のに持ってくる手法です。こちらも電気同様難易度を重視して易しい課目から攻略すると良いように思います。
エネルギー管理士の資格手当の相場
難易度が高い資格ですから、第二種電気工事の様な資格よりかは、手当てが大きいでしょう。会社の規模や規定にもよりますが、月額手当で5,000~15,000円。月額では支給されず、取得したときに資格取得金を支給するのみとなっている会社でも100,000円以上の資格取得金が見込めそうです。
エネルギー管理士を取得して良かったこと
エネルギー管理士を取得してよかったことは、
・エネルギー管理業務に関する経験が積めた
・難関資格を取れたという自分への自信ができた
・転職市場で自分の市場価値が増えたこと
です。
詳しくはこちらエネルギー管理士(エネ管)を取得して良かったこと
エネルギー管理士の業務で大変なこと
省エネのネタが見つからない
ある程度省エネ施策をやりつくした施設で次の省エネのネタが見つからないことがあります。そんなときは他の分野のエネルギー管理士試験を突破したエネルギー管理士に見てもらったり、他の施設の省エネ事例を見て勉強してうちの施設でも使えないかと検討したりします。毎年1%のエネルギー使用量逓減のノルマというのは地味にプレッシャーです。
物件オーナーが省エネ投資で首を縦に振らない
例えば蛍光灯をLED照明に代える提案を商業施設の物件オーナーに行ったときに、確実に大幅な省エネ効果が得られるのがわかっているのにも関わらず、物件オーナーが首を縦に振らないことがあります。それは、物件オーナーはテナントに電気を売っているので、電気を多く使ってもらわないと、その年度の売り上げ予算を達成できないのです。
その辺の大人の事情を目の当たりにしたときは、やるせない気持ちになりました。なかなか一筋縄ではいかないのだなと勉強になりました。
詳しくはこちらエネルギー管理士として省エネに取り組んだが頓挫した話
求められる人物像
探究心旺盛
エネルギー管理士は、建物内を巡回し省エネ化できそうな箇所を探して回ります。電気エネルギーは計測して数値化しなければ目に見えませんし、熱エネルギーについても計測しなければ目に見えません。目に見えない現象について測定器を通して数値で知り、何をすれば改善できるかを黙々と考え、周囲に相談しながら、試行錯誤を繰り返しつつ省エネの実績を出していく作業を業務としています。 例えるなら研究者の様な地道な作業を淡々とこなすことができる探究心が求められます。
数値に細かく事務処理を怠らない
どんな事務仕事でもそうですが、きちんと仕事内容を詰めてそれを文書にして、しかるべき時に提出して報告することは事務作業の基本です。世の中にはそんな基本ができていない人もいますが、エネルギー管理士の場合はその基本無くしては業務が成り立ちません。
日次、週次、月次、年次の計測値を集計し、整理し、省エネルギー会議や定期報告書様の資料を遅滞なく作成しなければなりません。 特に年に1度の経済産業省への報告に送れると、会社や組織に迷惑をかけることになりますので、忘れていたということにならないような事務管理能力が必要です。
エネルギー管理士の年収
エネルギー管理士であるというだけでは所属している組織で急に年収が上がることはありません。資格手当による月給の上昇は免状取得後すぐに反映されると思いますが、年収が大きく上がるのは所属している組織内での昇給に依ります。エネルギー管理士を取得することで、組織内での評価が上がり昇給が早くなるのであれば取得の効果は少し時間をかけて現れることになります。
年収の範囲は、所属している組織の給与水準や年齢階層によって大きく隔たりがあります。 例えば、新卒者が2年の実務経験を得てエネルギー管理士免状を取得した場合、年収はおそらく300万円~450万円程度になると思いますが、40代が取得した場合、500万円~800万円程度の年収が想定されます。(※所属する組織によって異なります。) ですので、エネルギー管理士であれば年収はこれくらいだとは一様に言えなそうです。
エネルギー管理士の市場価値
転職サイトに登録したところ、エネルギー管理士であるという点に評価を受けてオファーのメールをもらったことがあります。そのときの内容をご紹介します。ちなみに当時3ヶ月間ほど登録し、私登録したスペックは
・大卒
・建築設備関連工事の施工管理、ビル管理、エネルギー管理士の経験5年
・30代後半
でした。
ビルメン会社からのオファー
年収レンジ 300万円~450万円:当社が管理を受託している第一種指定工のエネルギー管理士に選任されて欲しい。
施工管理会社からのオファー
年収レンジ 450万円~600万円:省エネ診断を行い、省エネ投資を伴う工事を提案し、受注して欲しい。
工場、プラントからのオファー
年収レンジ 500万円~650万円:当社の第一種指定工場での年1%のエネルギー使用量削減が急務になっている。ぜひ省エネを進めていただきたい。 やはり、エネルギー管理士だから年収〇〇〇万円ぐらいという相場的な年収があるのではなく、所属する組織や行う業務によって大きく異なりそうです。
エネルギー管理士の将来性
将来性があるのかないのかと問われればある方だと答えるでしょう。しかし、とりわけバラ色かと言われるとそうでもありません。地球温暖化が進み、また国内の原発依存を減らしていく大きな情勢を考慮するとエネルギー管理士が省エネに取り組む社会的意義は大きいでしょう。
社会的意義が大きいからと言って給与水準の伸びが期待できるか、待遇の改善が期待できるか、急に転職市場での価値が上がるかというとそれはまた別のことになるでしょう。将来的にも現状維持程度だと思います。
けれども、期待できることが一つあります。それは、省エネ診断業務はAIには代替できないということです。倉庫管理や経理業務など将来的にAIに代替されそうとされている業種は多くありますが、人間が現地調査をして五感を駆使してエネルギーが過大使用されている状況を見つけ出して、その建築物と予算に応じた最適解を考え出すのはAIにはできません。そういう意味では将来性があると言えます。
まとめ
いかがでしたでしょうか、現役エネルギー管理士として知っていることを詰め込んでみました。エネルギー管理士のやりがいは、仮説と検証です。ここが怪しいと考えて、その箇所の省エネ施策を考えて実施し、その効果が出た時の喜びは癖になります。 今後エネルギー管理士の取得を考えている人は、ぜひ頑張って取得していただきたいと思います。
この勉強法で合格!エネルギー管理士(エネ管)[電気]合格体験記
この勉強法で合格!エネルギー管理士(エネ管)[熱]合格体験記